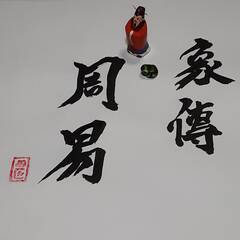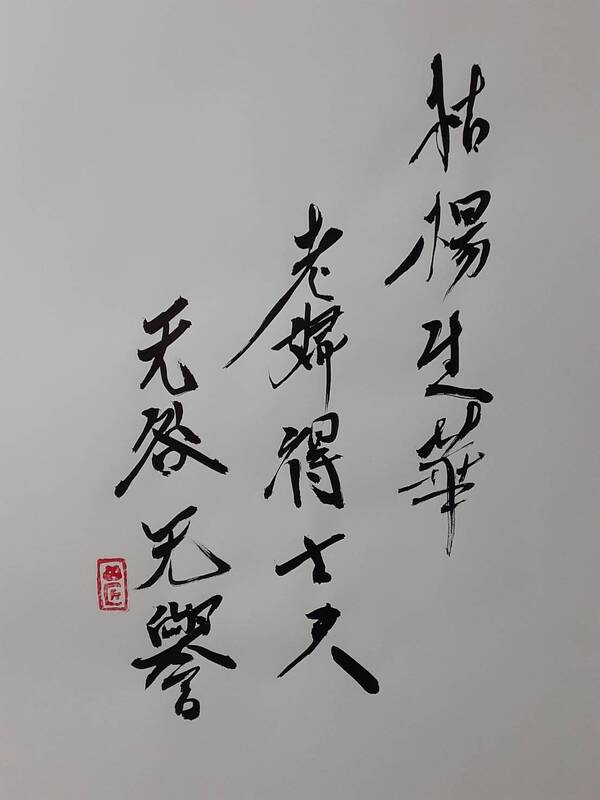
![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。
今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。
![]() 今回は「澤風大過(たくふうたいか)」五爻です。
今回は「澤風大過(たくふうたいか)」五爻です。

![]() 卦辞は「棟撓 利有攸往 亨」むなぎたわむ ゆくところあるによろし とおる。とあります。「山雷頤」でしっかり成長した後だからこそ限界に挑戦します。
卦辞は「棟撓 利有攸往 亨」むなぎたわむ ゆくところあるによろし とおる。とあります。「山雷頤」でしっかり成長した後だからこそ限界に挑戦します。
![]() そして「澤風大過」は「下卦」が成長を意味する「木」「風」である「巽(そん)」そして「上卦」が「沢」「沼」を意味する「兌(だ)」です、沼の下にある木、ということで沼で腐ってしまわないよう奮起する木なのです。
そして「澤風大過」は「下卦」が成長を意味する「木」「風」である「巽(そん)」そして「上卦」が「沢」「沼」を意味する「兌(だ)」です、沼の下にある木、ということで沼で腐ってしまわないよう奮起する木なのです。
![]() いや、腐っちゃうでしょ。大変そうだなー。
いや、腐っちゃうでしょ。大変そうだなー。
![]() 「山雷頤」で成長していなければ腐ってしまうでしょう。それが「澤風大過」です。
「山雷頤」で成長していなければ腐ってしまうでしょう。それが「澤風大過」です。
![]() 「五爻」は「枯楊生華 老婦得其士夫 无咎无誉」こようにはながしょうず ろうふそのしふをう とがなくほまれなし。
「五爻」は「枯楊生華 老婦得其士夫 无咎无誉」こようにはながしょうず ろうふそのしふをう とがなくほまれなし。
![]() どういう感じなの?
どういう感じなの?
![]() 「五爻」は「尊位」と呼ばれ「君主」や「偉い人」「実現」などの意味があります。ただ、生まれ変わるイメージの「澤風大過」としては、とりあえずの手を打った、という様なイメージもあるので「とが」も無いけど「ほまれ」も無い、と言っています。
「五爻」は「尊位」と呼ばれ「君主」や「偉い人」「実現」などの意味があります。ただ、生まれ変わるイメージの「澤風大過」としては、とりあえずの手を打った、という様なイメージもあるので「とが」も無いけど「ほまれ」も無い、と言っています。
![]() 「五爻」ですから、「中」を得ていることを、咎无、誉无、と言っているわけです。
「五爻」ですから、「中」を得ていることを、咎无、誉无、と言っているわけです。
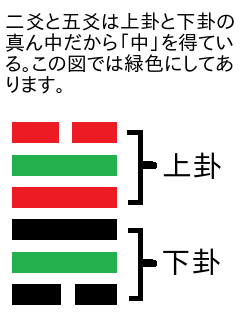
![]() そして「五爻」は「陽位」に「陽」で位、正しく強いイメージです。
そして「五爻」は「陽位」に「陽」で位、正しく強いイメージです。
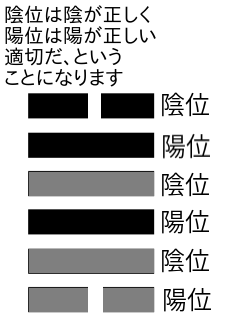
![]() その強い感じが「老婦」「夫を得る」なんだね。
その強い感じが「老婦」「夫を得る」なんだね。
![]() 強引という意味と、昔からの使命で本当にやりたいことを見つけた、という意味にもなります。
強引という意味と、昔からの使命で本当にやりたいことを見つけた、という意味にもなります。
![]() ただ、「上爻」には比していますが「四爻」には比していません。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)そして「二爻」に応じていません。「下卦」の「巽」の木には繋がらず、「兌」(沢、沼)の一番上とのみつながっています。
ただ、「上爻」には比していますが「四爻」には比していません。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)そして「二爻」に応じていません。「下卦」の「巽」の木には繋がらず、「兌」(沢、沼)の一番上とのみつながっています。
![]() そして「華」というのは命は短いものです。何かを生み出す、というより、変化の時、最後の時が近づきます。
そして「華」というのは命は短いものです。何かを生み出す、というより、変化の時、最後の時が近づきます。
![]() 「上爻」ではどうなるの?
「上爻」ではどうなるの?
![]() 没して生まれ変わります。
没して生まれ変わります。
![]() なるほどね。どっちにしても「咎无譽无」なんだね。
なるほどね。どっちにしても「咎无譽无」なんだね。
![]() 出典は「易経」でした。
出典は「易経」でした。