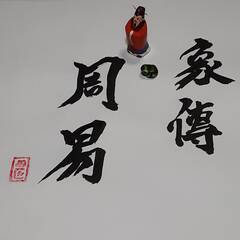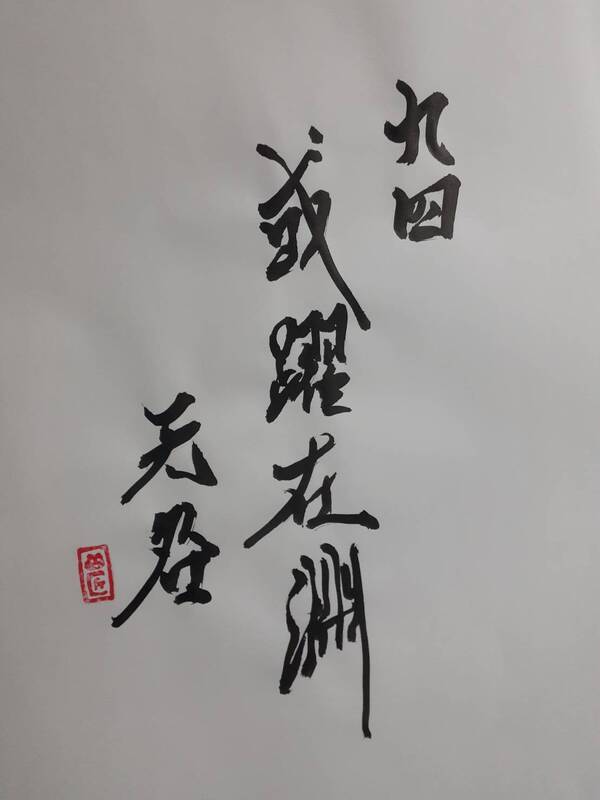
![]() 今回は特別企画「易経 十二消長卦」です。哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経 十二消長卦」になります。
今回は特別企画「易経 十二消長卦」です。哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経 十二消長卦」になります。
![]() 今回は「九四 乾為天 易経 十二消長卦」です。
今回は「九四 乾為天 易経 十二消長卦」です。

![]() 卦辞は「乾 元亨利貞」けん げんこうりてい。です。正しければ大いに亨る、ということですが、「乾為天」は自分を貫くイメージですので、それが「貞(ただしい)」ということです。
卦辞は「乾 元亨利貞」けん げんこうりてい。です。正しければ大いに亨る、ということですが、「乾為天」は自分を貫くイメージですので、それが「貞(ただしい)」ということです。
![]() 四爻は「或躍在淵 无咎」あるいはおどりてふちにあり とがなし。です。
四爻は「或躍在淵 无咎」あるいはおどりてふちにあり とがなし。です。
![]() 「下卦」が終わって「上卦」にやっと来たって感じだね。
「下卦」が終わって「上卦」にやっと来たって感じだね。
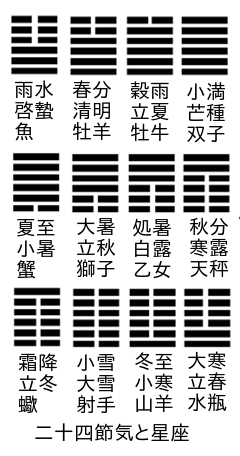
![]() 「二十四節気」的に言えば「小満」が終わって「芒種」と考えることが出来ますね、ようやく種まきの時と言えるでしょう。
「二十四節気」的に言えば「小満」が終わって「芒種」と考えることが出来ますね、ようやく種まきの時と言えるでしょう。
![]() 「乾為天」は時期的には「双子座」と重なるから、直感で情報収集をするイメージもあるよね。
「乾為天」は時期的には「双子座」と重なるから、直感で情報収集をするイメージもあるよね。
![]() そうです、ですから「下卦」では、何となく自分の形がつかめてくる形です。
そうです、ですから「下卦」では、何となく自分の形がつかめてくる形です。
![]() そうか、だから「初爻」では「潜龍 勿用」(せんりゅう もちうるなかれ)だったのか、まだ力が無いから用いちゃいけないんだ。
そうか、だから「初爻」では「潜龍 勿用」(せんりゅう もちうるなかれ)だったのか、まだ力が無いから用いちゃいけないんだ。
![]() 形にもなっていませんしね、そしてこの「上卦」では、踊りて淵に乗った、ので、まだ安定しない中にも段階が変わったと言えます。
形にもなっていませんしね、そしてこの「上卦」では、踊りて淵に乗った、ので、まだ安定しない中にも段階が変わったと言えます。
![]() 咎無し、ですから、やるべきであることが言えます、やらないと心残りになるイメージです。
咎無し、ですから、やるべきであることが言えます、やらないと心残りになるイメージです。
![]() 上手く行くの?
上手く行くの?
![]() そこは、後々どう思うか、は人それぞれですが、上手く行く、というより「やることで心残りが無くなる」という言い方ですね。
そこは、後々どう思うか、は人それぞれですが、上手く行く、というより「やることで心残りが無くなる」という言い方ですね。
![]() 「乾為天 四爻」は変爻すると「風天小蓄 四爻」ですから、孚(まこと)が重要だ、と言っていますので、「乾為天」では「自分の無意識」に忠実である、要するに素直さが必要だと言うことです。
「乾為天 四爻」は変爻すると「風天小蓄 四爻」ですから、孚(まこと)が重要だ、と言っていますので、「乾為天」では「自分の無意識」に忠実である、要するに素直さが必要だと言うことです。
![]() 種を蒔く感じだね。
種を蒔く感じだね。
![]() 自分の無意識とも言える「龍」が踊っているのですから、それに従うべきなのです。
自分の無意識とも言える「龍」が踊っているのですから、それに従うべきなのです。