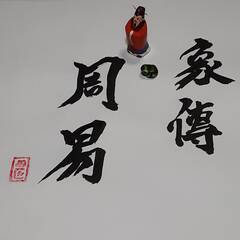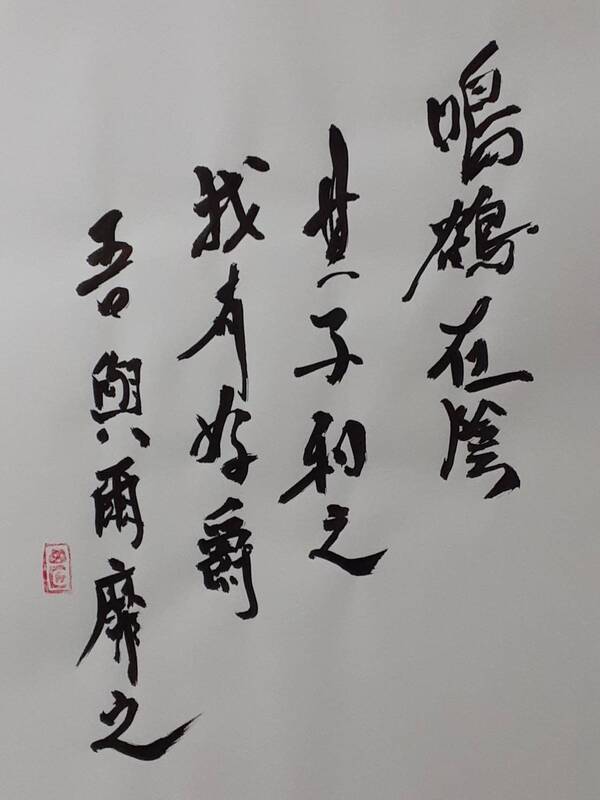
![]() 今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。
今回は特別企画「中国文学哲学としての易経三百八十四爻」です。占いではない哲学としての「易経」のお話です。カテゴリーは「易経三百八十四爻」になります。
![]() 今回は「風澤中孚(ふうたくちゅうふ)」二爻です。
今回は「風澤中孚(ふうたくちゅうふ)」二爻です。

![]() 卦辞は「豚魚 吉 利渉大川 利貞」とんぎょにしてきちなり たいせんをわたるによろし ただしきによろし。です。
卦辞は「豚魚 吉 利渉大川 利貞」とんぎょにしてきちなり たいせんをわたるによろし ただしきによろし。です。
![]() 「豚魚」?
「豚魚」?
![]() 「海の豚」はイルカ、「河の豚」はフグ、ですね。「江豚」はスナメリです。スナメリはイルカに似た魚ですが、風に向かっていく魚と言われていまして、下卦の「兌」の一番上の口が、上卦の「巽」要するに風、の方を向いているということです。
「海の豚」はイルカ、「河の豚」はフグ、ですね。「江豚」はスナメリです。スナメリはイルカに似た魚ですが、風に向かっていく魚と言われていまして、下卦の「兌」の一番上の口が、上卦の「巽」要するに風、の方を向いているということです。
![]() これは、お互いに信頼しあっている、惹きあっているイメージでもあります。
これは、お互いに信頼しあっている、惹きあっているイメージでもあります。
![]() 「下卦」の「兌」喜び、「三女」が「上卦」の「巽」従う、「長女」の様に成長するイメージもありますね。
「下卦」の「兌」喜び、「三女」が「上卦」の「巽」従う、「長女」の様に成長するイメージもありますね。
![]() そして「豚魚之信」という言葉がありますが、「豚魚」は心の鈍い人たちを指し、その「豚魚」でさえ感動させる徳があることを意味します。
そして「豚魚之信」という言葉がありますが、「豚魚」は心の鈍い人たちを指し、その「豚魚」でさえ感動させる徳があることを意味します。
![]() いろいろあるね。
いろいろあるね。
![]() そして「風澤中孚」の卦は「舟」の形でもあります。
そして「風澤中孚」の卦は「舟」の形でもあります。
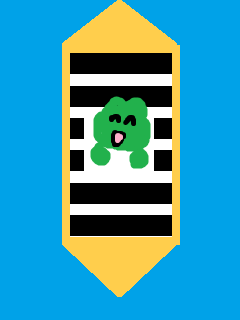
![]() どういう意味なの?
どういう意味なの?
![]() 「風澤中孚」は「上卦」が「木(巽)」で「下卦」が「沢(兌)」ですから、舟が浮かんでいるイメージでもあります。
「風澤中孚」は「上卦」が「木(巽)」で「下卦」が「沢(兌)」ですから、舟が浮かんでいるイメージでもあります。
![]() それで「大川をわたるによろし」なんだね。
それで「大川をわたるによろし」なんだね。
![]() 昔から中国では王朝が舟なら民衆が水であると言います、要するに噛み合ってこそ大川を渡れますし、水が荒れれば船は転覆してしまいます。
昔から中国では王朝が舟なら民衆が水であると言います、要するに噛み合ってこそ大川を渡れますし、水が荒れれば船は転覆してしまいます。
![]() そして「豚魚」「豚」と「魚」はよくある贈り物も意味します、贈り物の内容より信義、気持ちがあれば、喜ばれる、感動してもらえる、という意もあります。
そして「豚魚」「豚」と「魚」はよくある贈り物も意味します、贈り物の内容より信義、気持ちがあれば、喜ばれる、感動してもらえる、という意もあります。
![]() こういったことから「孚(まこと)」が通じる、と言うのが「風澤中孚」のテーマとも言えます。
こういったことから「孚(まこと)」が通じる、と言うのが「風澤中孚」のテーマとも言えます。
![]() 「二爻」は「鳴鶴在陰 其子和之 我有好爵 吾與爾靡之」めいかくいんにあり そのここれにわす われにこうしゃくあり われなんじとこれをともにせん。
「二爻」は「鳴鶴在陰 其子和之 我有好爵 吾與爾靡之」めいかくいんにあり そのここれにわす われにこうしゃくあり われなんじとこれをともにせん。
![]() どういう感じなの?
どういう感じなの?
![]() 離れた場所にいる親子の鶴がお互いに鳴き、声だけでも繋がろうとするイメージです。そして酒を酌み交わしたい、という思いによって、その気持ちを表現しています。「上卦」の「巽(そん、風、木)」は実は「逆さまにした兌」の形です。「下卦」の「兌(だ、沢、泉、杯)」はですから、「杯」と考えれば、上から杯を傾け、酒を注ぐようですね。
離れた場所にいる親子の鶴がお互いに鳴き、声だけでも繋がろうとするイメージです。そして酒を酌み交わしたい、という思いによって、その気持ちを表現しています。「上卦」の「巽(そん、風、木)」は実は「逆さまにした兌」の形です。「下卦」の「兌(だ、沢、泉、杯)」はですから、「杯」と考えれば、上から杯を傾け、酒を注ぐようですね。
![]() 成長した「上卦」の「木(巽)」が自分の得た「酒」を惜しむことなく「下卦」の「杯」に注いでいる、とすればそれこそ「孚(まこと)」と言えるでしょう。
成長した「上卦」の「木(巽)」が自分の得た「酒」を惜しむことなく「下卦」の「杯」に注いでいる、とすればそれこそ「孚(まこと)」と言えるでしょう。

![]() なるほどね。気持ちや心を注ぐイメージの卦なんだね。「二爻」はそのことを言ってるんだ。
なるほどね。気持ちや心を注ぐイメージの卦なんだね。「二爻」はそのことを言ってるんだ。
![]() 「二爻」は常に「中」を得ています、それはバランスをとり、中庸を得た行動をとるイメージです。
「二爻」は常に「中」を得ています、それはバランスをとり、中庸を得た行動をとるイメージです。
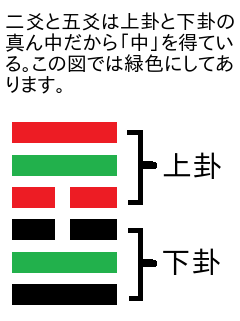
![]() なるほど。
なるほど。
![]() ただ「二爻」は「陰位」に「陽」ですから、力が足りない状況でも上の「五爻」につながろうとするイメージです。
ただ「二爻」は「陰位」に「陽」ですから、力が足りない状況でも上の「五爻」につながろうとするイメージです。
![]() 繋がりたいけど、繋がれない感じでもあるんだね。
繋がりたいけど、繋がれない感じでもあるんだね。
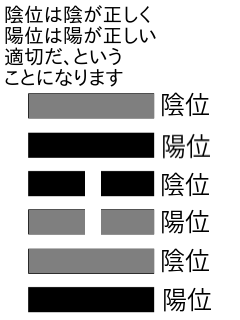
![]() ですから「二爻」は「五爻」に応じていません。
ですから「二爻」は「五爻」に応じていません。
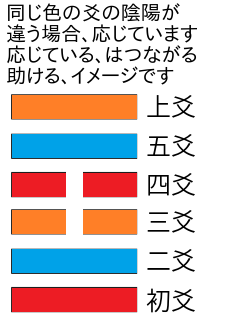
![]() ただ「二爻」は上の「三爻」に比し、「五爻」は下の「四爻」に比しています。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)
ただ「二爻」は上の「三爻」に比し、「五爻」は下の「四爻」に比しています。(隣の爻と陰陽が違う場合、比している、つながっています。)
![]() 繋がろうとしてるね!
繋がろうとしてるね!
![]() そうです、ですから、努力して自力でつながることで孚(まこと)を形に出来るとも言えるでしょう。
そうです、ですから、努力して自力でつながることで孚(まこと)を形に出来るとも言えるでしょう。
![]() ちなみに比した「三爻」は、「決めかねる」イメージです、良くなれば強気に、上手く行かなければ弱気に、と言うようでは「孚」とは言えない、とも言えますし、素直な気持ちを「孚」と取れる場合もあるでしょう。
ちなみに比した「三爻」は、「決めかねる」イメージです、良くなれば強気に、上手く行かなければ弱気に、と言うようでは「孚」とは言えない、とも言えますし、素直な気持ちを「孚」と取れる場合もあるでしょう。
![]() 要するに「二爻」はしっかりした気持ちを持てと言われてるんだね。
要するに「二爻」はしっかりした気持ちを持てと言われてるんだね。
![]() 「二爻」に比した「初爻」は「虞吉 有它不燕」おもんばかればきち たあればやすからず。ですからね。
「二爻」に比した「初爻」は「虞吉 有它不燕」おもんばかればきち たあればやすからず。ですからね。
![]() 余所見をするな、ってことか。
余所見をするな、ってことか。
![]() 出典は「易経」でした。
出典は「易経」でした。